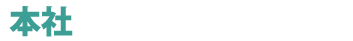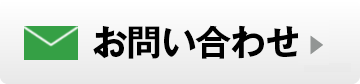土壌汚染対策法の調査 第4条による調査(その2)
平成22年3月5日の環境省の通達の一部を引用します。
解説②:環境省通達文の「ただし」書き
前項の通達で「掘削と盛土の別を問わず」とありますが、「ただし」書きが付記されています。
土地の形質の変更が盛土だけならば届出は不要です。
平成22年3月5日の環境省の通達の一部を引用します。
解説③:土地の形質の変更の例外
環境省の通達文には「土地の形質の変更の例外」が付記されています。
掘削の深度が50cm未満のとき、農業の日常的な業務、災害時の応急措置は土地の形質変更に該当しないということになります。
土間や基礎の解体は、わずかな範囲であっても50cm以上の掘削がともなうため、届出の対象です。
平成22年3月5日の環境省の通達の一部を引用します。
ア.軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの土壌汚染が存在するとしても拡散するおそれが小さいことから、適用除外とした(規則第25条)。このうち、同条第1号ロの「土壌の飛散又は流出」とは、土地の形質の変更を行う場所からの土壌の飛散又は流出をいう。
同号ハの「土地の形質の変更に係る部分の深さが50センチメートル以上であること」については、土地の形質の変更に係る部分のであれば、適用除外とはならない。
また、同条第2号の「農業を営むために通常行われる行為」とは、農地等(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地及び採草放牧地をいう。)において、農業者によって日常的に反復継続して行われる軽易な行為をいい、具体的には、耕起、収穫等を想定している。なお、土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく土地改良事業のように通常の土木工事と同視することができるものは、同号に該当しない。
イ.非常災害のために必要な応急措置として行う行為 緊急を要し、やむを得ない行為であることから、適用除外とした(法第4条1項第2号)。」
また、平成29年の法改正に伴い、土地の形質を変更しようとする最大深さより1m以上深い深度の汚染については考慮しない(試料採取等の対象にしない)ことができるようになりました。
土壌汚染対策法施行規則 第4条4項を引用します。
解説④:土地の形質の変更の届出の対象となる行為
解説①~③をつなぎ合わせると、土地の形質の変更の届出の対象となる行為は次のようになります。
深度50cm以上の掘削をともなう、掘削工事や盛土工事の範囲が3000㎡以上(現に有害物質使用特定施設が設置されている工場若しくは事業場の敷地にあっては、900㎡以上)となるときは、「土地の形質の変更」として届出が必要です。
届出の対象外となるのは、盛土のみの工事、日常的な農耕、災害時の応急措置です。
アスファルト舗装、土間や基礎の解体は、わずかな範囲であっても50cm以上の掘削をともなうものとされ、届出の対象となります。
土間や基礎の解体は、わずかな範囲であっても50cm以上の掘削がともなうため、届出の対象です。
解説⑤:だれが届出をするのか
第4条の条文では、「土地の形質の変更を使用とするもの」となっていますが、環境省の通達文で具体的に明記されており、届出者は、その工事の発注者です。
土壌汚染対策法の調査 第4条による調査(その1)
土壌汚染対策法の調査 第4条による調査(その3)